「社労士試験であと一歩届かず、悔しい思いをしていませんか?」
私も1年目はわずか1点届かず不合格。しかし、その失敗を活かした戦略で2年目に合格することができました。
この記事では、1年目の経験をバネに2年目の勉強法を見直し、本試験直前の気持ちの変遷やメンタルの揺れ動きまでをリアルに綴ります。
「自分だけじゃない」と安心したい方、「2年目、どう戦えばいいか」と悩んでいる方に、参考となる内容です。
はじめに|社労士試験2年目の挑戦
私は社会保険労務士試験に2年目のチャレンジで合格しました。
1年目はあと1点という悔しすぎる結果。その悔しさを原動力に、2年目は「絶対に合格する」という強い気持ちで学習に臨みました。
試験直前までの勉強の工夫、メンタルの保ち方、焦りへの対処…。そのすべてを振り返りながら、2年目の合格への道のりをお伝えします。
社労士試験|1年目と2年目の成績と勉強時間を比較
まずは、私の1年目と2年目の成績を比較してみましょう。
【 1年目の成績 】
- 勉強時間:772時間
- 選択式:28点(基準点割れあり)
- 択一式:44点(1点不足)
- 結 果:不合格(基準点割れ&総得点不足)
【 2年目の成績 】
- 勉強時間:604時間
- 選択式:33点
- 択一式:55点
- 結 果:合格!
不思議なことに、勉強時間は2年目の方が少なかったのです。 これは、1年目の失敗を活かして「効率」を意識した勉強に切り替えたことが大きな要因です。
私の勉強スタイル|2年目も直前期追い込み型
私は1年目も2年目も「直前期に一気に追い込む」スタイルです。
ただし、1年目は「動画視聴」を優先して、アウトプットに割く時間が足らずに、穴を作って不合格。 2年目はその反省から、「動画視聴」をカットして資料通信講座としてアウトプット中心へ。そして、2ヶ月前から一気に追い込むスタイルを貫きました。
【 使用教材:大原の資料通信講座 】
1年目で基礎はある程度固まっていたため、2年目は「講義を聴く」より「問題演習で知識を定着させる」ことを最優先にしました。
直前期追い込み型のメリット・デメリット
【 メリット 】
- 集中力が高く、記憶が定着しやすい
- 短期間で大量インプットのため、一気に知識がつながっていく
- 試験当日にピークを持っていきやすい
【 デメリット 】
- スタートが遅れると間に合わない
- 教材の取捨選択を間違えると失速する
- やり残しが増えるほど不安になり、集中力が落ちる
特に社労士試験は「基準点割れ」という制度があるため、特定分野の穴が致命傷になります。 直前の焦りをどうコントロールするかも最大のポイントです。
社労士試験|2年目の直前期のメンタルの推移
直前期のメンタルの変化は、日々の勉強に大きな影響を及ぼしました。 ここでは2年目の私の心の変遷を時系列で振り返ります。
| 時期 | 心境・行動 |
|---|---|
| 6月まで | 「2年目だから何とかなるかも…。いや、結構忘れてる。ヤバい」→ 焦りや不安がよぎるも、問題演習を繰り返すことでスピードが向上 |
| 6月後半(旅行前) | 「旅行までに一通り終わらせないと…」→ 択一式を優先し、選択式は直前に回す戦略へ変更 |
| 1回目の模試 | 「2年目だしB判定に入りたいな」→ 選択式B判定 / 択一式C判定 / 総合C判定 → 合格圏外 |
| 2回目模試(旅行後) | 「旅行で勉強が空いたけどB判定に入りたい」→ 選択式B判定 / 択一式A判定 / 総合B判定 → 少し光が見えた |
| 8月に入って | 「間に合わせる!旅行を言い訳にしない!」→ 追い込みに全力投球、知識がつながっていく感覚を得る |
| 本試験2週間前 | 「合計点では合格ライン。ただ、苦手分野と奇問難問が怖い」→ 対策として横断整理を強化 |
| 本試験1週間前 | 「択一式は大丈夫、選択式で穴をあけなければいける」→ 選択式問題集をざっくりチェック |
| 本試験前日 | 「あと1日欲しい…」→ 直前にマクロ経済スライドの暗記を実施 |
| 本試験当日(選択式終了) | 「いけた気がする」→ 基準点割れのない感触 |
| 本試験当日(択一式の間) | 「解いてて楽しい!」→ 知識を活かしながら自信を持って解答。未知の問題にも応用で対応 |
| 健康保険法の難問に遭遇 | 「ヤバい…足切りだけは避けたい」→ 他の知識を応用しながら解答するが、不安が残る |
| 択一式終了後 | 「健保法次第…でも大丈夫かも」→ 合格を確信しつつ、最後の不安が残る |
| 試験翌日~翌々日 | 「解答速報で確認、大丈夫そう!」 → 合格を確信 |
社労士試験|合格を引き寄せた5つのポイント
2年目で合格できた背景には、1年目にはなかった「意識の切り替え」と「戦略的な行動」がありました。
1. スキマ時間の活用
早めのエンジン始動は出来なかったものの、本格的に追い込む直前期は日々のスキマ時間もフル活用してアウトプットを徹底。
2. 教材の一本化とアウトプット中心
1年目は複数講座を並行し「動画視聴」に追われ、勉強した気になっていました。2年目は大原の資料通信講座に一本化し、問題演習を反復。
3. 選択式対策の強化
択一式問題集を完成させてから、選択式問題集に入りました。基準点割れの恐怖に対する自衛策として反復しました。
4. 横断整理
直前期には横断整理で知識を整理していきました。紛らわしい論点の対策となりました。
5. 自己暗示とメンタル維持
不安が押し寄せても「私は受かる」という信念を大切にしました。結果的に勉強効率が上がったと感じています。脳は自分が思った方向に働くと信じていました。
社労士試験は勉強と同時に「メンタル試験」
社労士試験は、知識の勝負であると同時に、メンタルの勝負でもあります。
特に直前期は、
- 不安との戦い
- 焦りのコントロール
- 過去の失敗の影に打ち勝つことが求められます。
私が実践したメンタル維持法は、
- 「受かる」という信念を持つ
- 不安になったら反復している問題集で自信回復
- 過去の模試の結果との比較を「成長の証」として見る
ポジティブな自己暗示を繰り返すことで、焦りやネガティブ思考を減らし、安定した心で試験に臨めました。
社労士試験から得たもの|勉強の成果は合格だけじゃない
2年間の社労士試験への挑戦を通じて、私は「合格」だけでなく、人生にとって大きな財産を得たと感じています。
- 集中力と継続力:毎日勉強を続けることで、習慣化の力を実感
- 自己管理能力:スケジュール管理と体調管理の大切さを学習
- メンタル耐性:失敗を経験したからこそ、ブレない心を獲得
まとめ|2年目の合格要因
2年目で社労士試験に合格できたのは、1年目の失敗を正面から受け止め、戦略を練り直し、最後までメンタルを崩さなかったからです。
- 直前期追い込み型でも、エンジン始動は早めに限る(2年目も反省を込めて)
- 教材を絞り、アウトプットを重視
- 模試や答練で現状を把握し、弱点に集中
- 選択式対策を怠らず、基準点割れを防ぐ
- 最後は「自分を信じる力」が鍵になる
あと一歩届かなかった悔しさをバネに、合格につながりました。この記事が、あなたの合格へのヒントになることを心から願っています。
関連記事|合わせて読むならこちら!
『社労士試験1年目|勉強・メンタルのリアル』はこちら!

『社労士試験の勉強時間は実際どれくらい?|合格者が語る1年目の記録と成績』はこちら!

『社労士試験の勉強時間は実際どれくらい?|合格者が語る2年目での合格記録』はこちら!





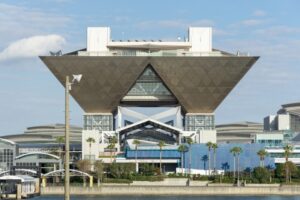


コメント