はじめに|「精度と速度」は、電卓という“武器”で磨かれる
簿記の学習において、知識と同じくらい重要なのが「電卓スキル」です。
特に日商簿記2級や1級のように、試験範囲が広く、かつ実務的な処理力が問われる級になると、いかに電卓を正確かつスピーディーに扱えるかが、得点力を左右します。
私は独学で日商簿記2級・1級の両方に合格しましたが、2級の勉強を始めた当初は「問題文の意味は分かるのに、時間が足りず最後まで解ききれない」ということが何度もありました。
しかし、繰り返しトレーニングを重ねることで、電卓を叩くスピードが上がり、計算ミスも激減。最終的には全体を見渡しながら、落ち着いて解き進められるようになりました。
そして簿記1級では、出題範囲がさらに広がり、計算処理の複雑さも段違いになります。だからこそ、電卓の「精度と速度」は試験突破の鍵になります。
この記事では、簿記2級から1級までを見据えて、おすすめの電卓、独学でも実践できるトレーニング法、そして意識すべきポイントを、私の実体験を交えて丁寧にご紹介します。
なぜ電卓スキルが重要なのか|簿記試験は“時間との戦い”
簿記の試験において、電卓を使う場面は当たり前のように出てきます。
しかし、単なる“計算ツール”と甘く見ていると、試験本番で痛い目を見ることになります。
たとえば日商簿記2級は、3級の延長線上にあるように見えて、実際は別物です。
単なる仕訳では終わらず、精算表や試算表などに数値を埋めていく処理が求められ、問題文の読解にも時間がかかります。
この過程で、ちょっとした計算ミスやタイムロスが致命傷になることも少なくありません。
さらに1級になると、論点がより専門的になり、仕訳の量も増大。
一つの問題に対して複数のステップが必要になるため、計算精度と処理速度の両立が不可欠になります。
だからこそ、
「いかに正確に、いかに速く電卓を叩けるか」が、試験本番での余裕につながるのです。
「精度」が求められる理由
いくらスピーディーに計算しても、答えが間違っていては意味がありません。
しかも簿記の問題は連動していることが多く、1カ所のミスが連鎖的に後半の問題にも影響してしまうのが怖いところ。
特に、一つの仕訳ミスが後の問題に波及するケースもあるため、正確なキー操作と、見直し力は必須のスキルになります。
「速度」が求められる理由
- 試験時間が限られている(2級:約90分/1級:約180分)
- 問題文の読解と計算処理を交互に行う必要がある
- 焦りや疲れによって、ケアレスミスが起きやすくなる
このように、試験時間内で解ききるためには、電卓スキルが“得点力を左右する武器”になるといえます。
私が愛用した電卓と、電卓スキル向上に参考にした書籍
私は、日商簿記2級から1級までをすべて独学で学び、合格を果たしました。その過程で強く感じたのは、電卓が単なる“計算ツール”ではなく、試験を戦い抜くための相棒のような存在になるということです。
特に試験本番では、時間との勝負になる場面も多く、正確な計算とスピードを両立できることが、得点力に直結します。だからこそ、信頼できる電卓と、それを使いこなす力が欠かせません。
私が愛用していた電卓|カシオ「JS-20WK」
簿記2級の学習を始めたときから、私が一貫して使っていたのが カシオの「JS-20WK」 です。
この電卓は、12桁表示でキーの打ち心地が非常によく、指の疲れを最小限に抑えてくれる設計になっています。キーの反発も適度で、長時間の使用でもストレスが少なく、スピーディかつ正確な入力がしやすい点が特に気に入っていました。
また、簿記試験で必要とされる機能がしっかり搭載されているのも魅力で、2級はもちろん、1級でも十分に対応できるスペックです。個人的には、独学において「使い慣れた道具を使い続ける」ことの安心感も大きな武器になったと感じています。
日商簿記2級・1級はもとより、税理士・公認会計士試験を見据えた学習にもぴったりの一台です。
試験本番だけでなく、日々の学習でもストレスなく使えるのが大きな魅力です。
電卓スキル向上に役立ったおすすめ書籍
電卓の操作に自信がない方、またさらにスキルを高めたい方には、以下の一冊がおすすめです。私も参考にしてとても役立ちました。
- 『カンタン電卓操作術 第3版』(TAC出版)
この本は、電卓の基本的な使い方から応用テクニックまで、簿記・税理士・会計士などの受験生向けに丁寧に解説されています。
操作のコツや手の動き、練習問題などが豊富に収録されており、「精度と速度の両立」を実現するための実践トレーニングができます。さらに、収益認識基準や軽減税率といった最新の会計ルールにも対応しているため、今の試験傾向に沿った形で学べるのもポイントです。
なお、「収益認識基準」や「軽減税率」などの新制度に関する記述は受験する試験の対策として不要な場合は、それらの部分は読み飛ばして問題ありません。
(軽減税率は2級で一部出題される可能性がありますが、本書の内容は補足程度と考えてOKです)
電卓スキルは、すべての級に通じる“基礎力”
簿記2級だけでなく、簿記1級や税理士・公認会計士試験を視野に入れている方にとって、電卓スキルは早い段階から鍛えておくべき基礎力です。
特に独学で学習を進める方にとっては、信頼できる電卓と、確かなトレーニング教材の存在が、合格への大きな助けになります。
「正確に、速く計算できる自分」を育てていくことが、簿記の学習においては何よりの時短になり、試験本番での安心感にもつながります。
独学でも実践できる電卓トレーニング法|精度と速度を鍛えるコツ
簿記の試験では、「正しい仕訳を書ける」「計算の仕組みを理解している」だけでは不十分です。
重要なのは、それらを限られた時間内に正確に解ききる力。これは、特に2級・1級レベルでは試験合否を左右するポイントになります。
独学で学習を進める場合はなおさら、本番を意識した電卓操作のトレーニングが欠かせません。
まず決めておきたい操作スタイル
- 電卓を右手で打つのか、左手で打つのか?
- 電卓とペンの使い分けをどうするのか?
私の感覚では、右利きの人の多くが「電卓は左手・ペンは右手」というスタイルを取っています。左手で電卓を操作しながら、右手で素早く解答を記入する流れです。
ちなみに私は、右手一本でペンを握ったまま電卓も操作し、そのまま解答を書くというスタイルで通しました。
どちらのスタイルが正解というわけではなく、自分が一番スムーズに動ける形を早めに決めておくことが重要です。
電卓トレーニングの基本は「繰り返し」
電卓スキルの向上で最も効果的なのが、「繰り返し」です。
新しい問題ばかり解くのではなく、一度解いた問題を何度も繰り返すことで、操作に“慣れ”が生まれます。
たとえば、
- 同じ仕訳問題を3回以上解く
- 指の動き、計算の順序、答えを記入する手の動作まで、一連の流れを体で覚える
- 慣れてきたら、「○分以内に解く」と時間を決めて挑戦する
このようなトレーニングを積むことで、自然と精度と速度の両方が高まっていきます。
試験本番に効く「小さな工夫」
- 電卓の位置は毎回同じ場所に置く(手の動きを固定)
- 手元を見ずに電卓を打つ練習をする(=視線は常に問題文へ)
- 打鍵音やリズムにも注目して、「心地よく打てる」感覚をつかむ
地味なようで、こうした細かい工夫の積み重ねが、試験本番での「安定感」につながります。
まとめ|電卓スキルは簿記試験を突破する“もうひとつの武器”
簿記の学習というと、「テキストの読み込み」「仕訳や決算整理の理解」「問題演習」が中心と思われがちですが、試験本番での得点力を高めるためには、“電卓スキル”が欠かせない要素となります。
特に日商簿記2級・1級では、問題文のボリュームや計算量が多く、限られた時間の中で正確に解答を導き出すスピードと安定感が求められます。
私自身、2級・1級ともに独学で学習し、いずれも一度の受験で合格しています。
とはいえ、練習を重ねる中では「時間切れで最後まで解けない」「焦ってケアレスミスをしてしまう」といった場面も多くありました。
ですが、電卓操作を意識的にトレーニングし、繰り返し練習を積むことで、操作のスピードも正確性も徐々に上がっていきました。
ポイントは、同じ問題を何度も解くことで、計算のリズムや手の動きを“体で覚える”こと。
そして、自分に合った電卓と、日々の学習の中で電卓スキルを意識的に鍛えていくことが、合格への近道になります。
簿記試験は、知識だけでなく実務的な処理力と判断力も試される試験です。
だからこそ、「電卓はただの道具」とは捉えず、試験を戦い抜くための“頼れる相棒”として、しっかり付き合っていきましょう。
関連記事|合わせて読むならこちら!
『日商簿記2級を目指した理由』はこちら!

『資格を取っても人生は変わらない?|中小企業診断士が教えてくれたキャリアの広がり』はこちら!

『資格を取っても人生は変わらない?|中小企業診断士が教えてくれたキャリアの広がり』はこちら!


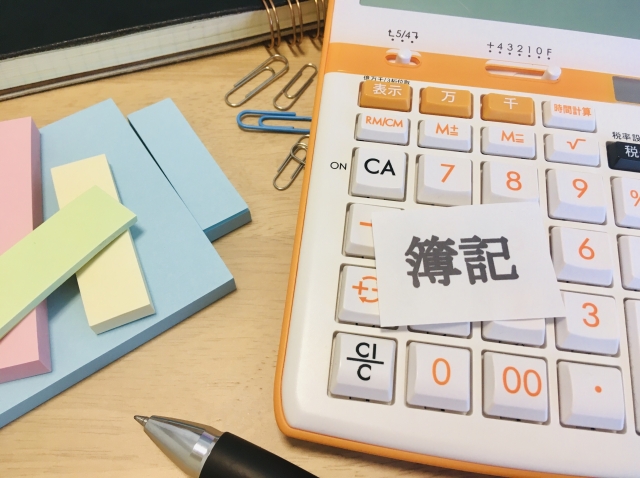

コメント