はじめに|中小企業診断士試験に独学でストレート合格
「独学で中小企業診断士試験にストレート合格できるの?」
そんな疑問を持っている方に向けて、私の体験を共有します。
私は、中小企業診断士試験に1年目でストレート合格(1次・2次試験を同年度に合格)しました。それだけでも珍しい部類かもしれませんが、実はその間に、長男の誕生、転勤、引っ越しなど、人生の大きなライフイベントがいくつも重なっていたのです。
限られた時間と環境の中で、合格まで辿り着いた勉強時間の記録をお伝えしていきます。
特に「働きながら」「家庭と両立しながら」合格を目指している方にとって、この記事のリアルは「私でもできる!」とモチベーションにつながるものと思います。
中小企業診断士試験は、ビジネス全般にわたる広範な知識と、論理的思考を問われる試験です。独学だからこそ、自分に最適な方法を見つけて工夫する力と効率的な学習が求められます。
この記事が、忙しい日常の中でも合格を目指すすべての方の背中を押せる内容になるように、できるだけ具体的にお伝えしていきます。
この記事でお伝えすること
- 試験シーズン中に私が経験したライフイベント
- 限られた環境下での実際の勉強時間とその管理方法
- 忙しくても合格できる、効率的な学習方法のポイント
- 合格のための2次試験での工夫
この記事は次のような方におすすめです
- 中小企業診断士試験の受験を検討している方
- 合格までに必要な勉強時間の目安を知りたい方
- フルタイムで働きながら、または子育てしながらの合格体験を知りたい方
- 勉強を始めたいけど、時間が確保できるか不安な方
- 独学合格のリアルを知って、自分の学習戦略を見直したい方
中小企業診断士試験|1次試験までの勉強時間
私が1次試験までに確保できた勉強時間は、合計475時間30分でした。
実は当初、約650時間を確保する予定で計画を立てていました。しかし、子どもの誕生や転勤、引っ越しといったライフイベントが重なり、現実は想定よりもかなり短くなってしまったのです。
それでも合格できたのは、学習の進捗をしっかりと管理しながら、限られた時間を最大限に活かす工夫があったからだと思います。
特に、限られた時間の中で「何をやらないか」を見極めることは、非常に重要でした。すべてを完璧にやろうとすると、時間も体力も足りません。私は過去問と要点整理に集中し、無理なく回せるサイクルを作りました。
学習計画と勉強時間の記録方法
私はExcelを活用して学習計画表を作成し、日々の勉強時間を記録していました。記録することで、どの科目にどれだけ時間を使ったか、どの時期に集中して取り組めたかなどが「見える化」され、科目ごとの進捗や対策を把握するのにとても役立ちました。
Excel以外にも、Studyplusなどの学習管理アプリも有効です。重要なのは、自分の学習を可視化することです。これにより、忙しい毎日でもモチベーションが保てますし、学習の習慣化にもつながります。
たとえば、「今日はたった30分しかできなかった」と思っていても、1週間で見ると「意外と10時間以上できている」こともあります。記録は、そういった積み重ねの「見える化」でもあるのです。
1次試験までの実際の勉強時間
実際に使用していたExcelはこちら。

実際の勉強時間の結果はこちら。

- 当初の学習計画:650時間を目標
- 実際に確保できた時間:475時間30分
記録のメリットは以下のとおりです。
- 学習量の見える化で達成感が得られる
- 科目ごとの時間配分のバランスを改善できる
- どの科目に時間が偏っていたかを把握できる
- 学習の振り返りができるので改善サイクルが回せる
スキマ時間を活用した「時短学習」も重要でした。具体的には、通勤中に過去問題集を解いたり、昼休みに30分間を問題演習に充てたりです。そうした「細切れ学習」を積み上げていくことが、結果的には大きな成果につながったと感じています。
中小企業診断士試験|試験勉強とライフイベントの両立
私の受験シーズンは、まさにライフイベントの連続でした。以下の表は、その時期に起きた主な出来事を時系列でまとめたものです。
ライフイベントの時系列
| 月 | 出来事 |
|---|---|
| 2月 | 長男誕生 |
| 4月 | 長女が幼稚園入園 |
| 6月末 | 転勤の内示 |
| 7月 | 荷造り・家探し・引っ越し準備 |
| 8月初旬 | 1次試験を新幹線で受験地へ |
| 8〜9月 | 新任地での仕事・引っ越し片付け |
| 娘の転園、長男は生後6ヶ月 | |
| 10月 | 2次試験 |
このように、試験直前の7月〜10月にかけて最も忙しく、勉強に集中できる時間は非常に限られていました。
だからこそ、1次試験の勉強の延長線上で2次試験にもつながる学習法を意識していました。知識をただ覚えるのではなく、実際に使える形にする「アウトプット重視」の勉強を心がけていました。
また、家族の理解と協力も欠かせませんでした。妻に中小企業診断士試験を目指すことを話し、理解をしてもらったことで環境を整えることができました。家族とのコミュニケーションも、合格に向けた大切な要素のひとつだと思います。
中小企業診断士試験|2次試験の勉強時間と対策
ライフイベントをこなすことで精一杯だったため、2次試験対策としての学習時間の記録は残念ながらできていません。しかし、体感ベースでは約80時間ほどでした。
2次試験では、1次試験のように知識を問うというよりも、与件を読み取って論理的に解答を構成する「実践型の試験」です。そのため、時間が少ない中でも、以下のポイントに絞って効率的に勉強を進めました。
2次試験対策のポイント
- 答案練習を重視する
- 問題を解く中で、解法プロセスと解答作成プロセスの「自分の型」を見つける
- 模試で本番をシミュレーション
- 時間配分や「自分の型」を本番さながらに実践する
- 復習を徹底する
- 解いた問題は必ず復習し、どこが曖昧だったかをチェック。「自分の型」を磨く
模試や過去問の振り返りは、2次試験対策における最大の学びの場でした。とにかく1回の模試に対して、与件文と設問に向き合い事例問題の構造を理解する意識で取り組みました。
まとめ|時間の工夫で中小企業診断士試験に合格できる!
中小企業診断士試験は、確かに難関資格の一つです。しかし、働きながらでも、家庭と両立しながらでも、工夫次第で短期間で合格することは十分可能です。
ここでは、私が感じた「短期間合格のためのポイント」を整理しておきます。
短期間合格のポイント
- スキマ時間を活用する
- 通勤時間・昼休みなどを有効活用し、過去問などの反復演習を行う
- 学習の優先順位を明確にする
- 頻出分野を集中して学習し、得点効率を上げる
- 記録をつけてモチベーション維持
- ExcelやStudyplusなどの学習管理アプリを使って進捗を見える化
- 柔軟に計画を修正する
- 計画通りに進まなくても、軌道修正できる仕組みを作っておく
- 勉強時間の偏りを避ける
- 足切りを防ぐため、どの科目もバランスよく学習する
合格までの道のりを振り返って感じるのは、「勉強時間の多さ」よりも「勉強の質」が大切だということです。誰しもが「勉強時間の多さ」にこだわりがちですが、確保できない勉強時間を嘆くよりも、短くても確保できた時間の「勉強の質」を向上させることに意識を向ける方が合格に近づきます。
忙しい中でも合格を目指す方は、まずは学習計画をざっくりでよいので立ててみてください。そして、試験日から逆算して、どこに重点を置くべきかを見極めましょう。
あなたの努力が実を結びますように。
中小企業診断士試験の合格を心より応援しています!
関連記事|合わせて読むならこちら!
『社労士試験の勉強時間は実際どれくらい?|合格者が語る1年目の記録と成績』はこちら!

『社労士試験の勉強時間は実際どれくらい?|合格者が語る2年目での合格記録』はこちら!

『日商簿記2級を目指した理由|中小企業診断士の次に見えた「会計の武器」』はこちら!



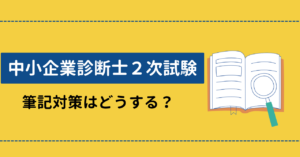




コメント