「社労士試験であと一歩届かず、悔しい思いをしていませんか?」
そんな悔しさを味わった方は、決して少なくないと思います。私もまさにその一人でした。1年目は択一式でたった1点届かず、さらに選択式でも基準点を割ってしまい不合格に。まさに「あと一歩」の現実を突きつけられた瞬間でした。
しかし、その経験がなかったら、私は2年目の合格を手にすることはできなかったかもしれません。1点差の不合格を「糧」にすることで、私は戦略を見直し、メンタルの持ち方を変え、2年目の挑戦で社労士試験に合格することができました。
この記事では、私自身の1年目の試験直前の気持ちの推移と勉強内容を振り返りつつ、2年目にどのように学習法とマインドセットを改善したのかを詳しくご紹介します。特に「直前期の過ごし方」や「焦りよう」は、これから試験に挑む方の大きな参考になるのではないでしょうか?
最後まで読んでいただければ嬉しいです。
はじめに|社労士試験2年越しの挑戦、合格への入口
社会保険労務士試験に挑んだ2年間は、単なる試験勉強を超えて、自分と向き合う時間でもありました。 1年目の不合格は残念ではありましたが、それは終わりではなく、次のステージへの入口でもありました。
試験に落ちたとき、正直なところ「直前期にやり切った感」 もあり 「もういいかな」と思ったこともありました。 でも、試験直後に悔しかったあの気持ちは、確かに「本気だった証拠」。 だからこそ、あの経験を無駄にしたくないと強く思い、2年目の挑戦を決めました。
社労士試験の勉強時間と成績の比較
まず、1年目と2年目の試験結果を具体的に比べてみます。
【 1年目の成績 】
- 勉強時間:772時間
- 選択式:28点(基準点割れあり)
- 択一式:44点(1点不足)
- 結 果:不合格(基準点割れ&総得点不足)
【 2年目の成績 】
- 勉強時間:604時間
- 選択式:33点
- 択一式:55点
- 結 果:合格!
「勉強時間が少ない方が合格する」というのは、1年目の記憶が残っているというだけではなく、効率と戦略がどれだけ重要かを物語っています。 やみくもに時間を積み重ねるのではなく、どこに力を入れ、どこを捨てるか。 その判断力が勝負を分けたのです。
社労士試験|1年目の教材と勉強
1年目は、フォーサイトと社労士24を併用していました。
通信講座でのインプットが中心で、動画視聴をベースにテキストと見比べるというスタイル。ただ、この「動画視聴」が目的化してしまい、インプット偏重型になっていた感があります。 「講義を最後まで見ないと問題演習に進めない」と、謎のルールを自分の中に作ってしまっていたんです。
結果、アウトプットが明らかに足りなかったです。手を動かして覚えることに時間を割けなかった自覚は今ならあります。 振り返れば、「勉強している気になっていた」時間がとても多かったと反省しています。
社労士試験|1年目の失敗から学んだ直前期の勉強の落とし穴
1年目の不合格の要因は明確でした。やるべきことができていなかった。ただそれだけです。
【 反省点まとめ 】
- アウトプット不足:動画視聴の消化に追われ、問題演習の量が圧倒的に足りなかった。
- 選択式対策の甘さ:動画視聴に追われた分、選択式対策を後回しにした。
- 詰め込み型の弊害:答練を後回しにして直前期に集中投入→終わらなかった。
- メンタルの浮き沈み:未消化の教材を見るたびに焦り、最後は手つかずの教材は捨てる分野に。
これらの経験を経て、「学習の優先順位」と「焦りのコントロール」の重要性を痛感しました。
私の勉強スタイル|直前期追い込み型のリアル
私は基本的に、直前期に一気に火がつく「追い込み型」の人間です。 集中力が出たときはとことんやるタイプで、1日10時間以上勉強することもあります。
【 メリット 】
- 集中力が高く、記憶が定着しやすい
- 短期間で大量インプットのため、一気に知識がつながっていく
- 試験当日にピークを持っていきやすい
【 デメリット 】
- スタートが遅れると間に合わない
- 教材の取捨選択を間違えると失速する
- やり残しが増えるほど不安になり、集中力が落ちる
社労士試験のように「基準点割れ」がある形式では、穴が命取りになります。 この試験には「捨て科目」「捨て分野」はないと学びました。
社労士試験|1年目直前期のメンタルの推移
| 時期 | 心境・行動 |
|---|---|
| 試験2ヶ月前 | 「全範囲終わっていない…」 → 模試C判定(合格圏外) |
| 試験1ヶ月前 | 「少し伸びたかも!」 → 模試B判定(希望の光) |
| 3週間前(8月) | 「やるしかない!」 → 模試と答練の追い込み開始 |
| 2週間前 | 「間に合うかも?」 → 記憶が整理されてきた感覚 |
| 1週間前 | 「間に合わせる!」 → 自信が芽生えはじめる |
| 試験前日 | 「あと1週間あれば…」 → やり残した感あり |
| 試験当日(午前) | 「ギリギリ7割いけたかも?」 → 実は基準点割れしている |
| 試験当日(午後) | 「合格ラインいけた気がする」 → 選択式で割れていたとは気づかず |
| 解答速報後 | 「終わった…」 → 不合格確定 |
この一連の心の動きは、今も鮮明に覚えています。そして、2年目の戦略を練る際の最大のヒントにもなりました。
社労士試験|勉強法のヒントを得て2年目へ
2年目は「アウトプット中心で進めて、いかに直前期に総復習を確保するか」という学習戦略を立てることにしました。
社労士試験|2年目の学習戦略
- 早めのエンジン始動:追い込み型は維持しつつ、朝1時間の早起き、通勤時間、移動時間、昼休みを活用して計画的に学習。
- スキマ時間の活用:問題演習の反復
- アウトプット中心:大原の資料通信講座をメインに、動画視聴をカットしてアウトプット重視に転換
- 総復習の徹底:1ヶ月前には総復習を完了し、余裕を持って直前期へ。
「完璧は目指さない。苦手を作らず、7割主義で合格点を確保する」
この意識で2年目へつなげることにしました。
社労士試験のメンタル維持|「信念」が合格を引き寄せる
最後の鍵を握るのは、「心の持ち方」
1年目は「落ちたらどうしよう」という不安と「思ったよりも勉強時間が取れないから仕方がない」という思考を持っていました。ですが、勉強中、特に試験直前期は、知識と同じくらいメンタルが重要です。「受かる信念」を持つべきです。
- 自分は「受かる」と言い聞かせる
- 合格後の姿をイメージする(名刺に“社労士”と書かれる日を妄想するなど)
- 小さな達成感を積み重ねつつ、自己肯定感を高める
脳は自分が思った方向に働くからこそ、ポジティブな自己暗示は脳の働きを変えると言われています。不安が襲ってきたときほど、自分の軸を信じることが力になります。
振り返ると、1年目はこの「受かる信念」が弱かったと思います。そして「信念」より「不安」が勝ると、勉強効率も落ちていくと感じています。
社労士試験の勉強で得たもの|点数以上の成長
1年目の社労士試験に挑戦したことで、私は不合格ながらも貴重な経験を手にしました。
- 短期間で追い込んだ集中力と瞬発力
- 2年目につながる学習戦略のヒント
- 挑戦し続けるメンタル
この経験は、試験だけでなく、仕事や人間関係にもポジティブな影響を与えてくれています。
まとめ|失敗から学び、合格へとつなげる力
社労士試験において、失敗は決して無駄ではありません。
- 失敗は次の挑戦へのヒントになる
- 量より質、そしてメンタルを整えることが合格のカギ
- 挑戦した過程そのものが力になる
あと一歩届かなかったとしても、その経験は自分を成長させてくれるチャンスになります。
この記事が、同じように試験に挑戦するすべての方の背中を、そっと押す存在になれば幸いです。
関連記事|合わせて読むならこちら!
『社労士試験2年目|勉強・メンタルのリアル』はこちら!

『社労士試験の勉強時間はどれくらい?|合格者が語る1年目の記録と成績』はこちら!

『社労士試験の勉強時間はどれくらい?|合格者が語る2年目での合格記録』はこちら!





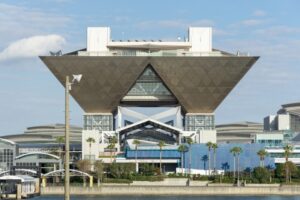


コメント